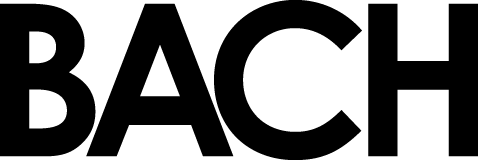幅允孝は『緒方 野趣と料理』を見て、 写真が匂うことを知った。
幅允孝は『緒方 野趣と料理』を見て、写真が匂うことを知った。
昨今、誰もが食べものの写真を撮り、個々のSNSコミュニティで共有しているなか、料理写真のプロフェッショナルたちは何を考えているのだろう?
先日、「日本食文化会議2017」なるシンポジウムの末席を汚したのだが、そこで料理写真家の越田悟全さんに出会った。もちろん、彼の仕事は本を通してよく見ていたし、
その美しい食べ物の写真はじつに印象的だったのだけれど、直接話を聞くことで、とても好い刺激を受けた。
1957年生まれの越田さんは食専門出版社の柴田書店からキャリアを始め、1985年に独立。大阪「大和屋」や徳島「青柳」など日本料理の名店のみならず、スペインの「エル・ブジ」やN.Y.の「ゴッサム・バー&グリル」などの料理写真も手掛け出版している。
僕ら、普通の人が食べ物の写真をSNSに投稿する時は、(自慢であれ欺瞞であれ)基本的には自己承認を求める心が働いている。あとは、「生きています」という報告というか。
一方、越田さんの料理の写真は、よい意味で「不穏」である。つまり、穏やかでない。例えば、最新刊『緒方 野趣と料理』では、一皿、一皿の料理やその素材、手業、そして器と料理の邂逅によって生まれる空気までもが写真化されていた。それは、料理人や素材と切るか切られるかの勝負をしているようでもあった。
世間でいわれる「SNS映え」という観点における「いかにもおいしそう〜」とは、全く違った食の写真である。実際、彼は徳島県の「青柳」料理を撮影するため、一家で一年間だけ徳島に引っ越したという。越田さんの料理に向かう写真は、執念というより狂気に近いのかもしれない。
日本料理の椀物の写真を撮る際は、蓋をどれくらいの時間かぶせておいたかによって漆の器の縁につく水滴の大きさが変わってくる。その時間を入念に計算し、もっとも適切な椀の水滴を求めて彼は日々写真に向き合っているのだ。その厳密さと集中力こそ、これからの人間の仕事を示唆すると僕には思えた(その嗅覚はAIに駆逐されそうもない)。
越田さんの料理写真の最大の特徴は「想像力を働かせる奥行き」だと僕は思う。誰もがよく見る料理レシピの写真を例に語ってみよう。当然おいしそうに撮られているのだが、読者がその写真を見て試みることは「100点満点=レシピ写真」に努力し近づけていく行為だ。「今日はよく似せてできたから93点」とか、「今日は色味が全く違ったから75点」といった具合に。
一方で、越田さんの写真は100点満点の向こう側に読者を運ぶ写真だと思う。その料理をトレースするつもりで写真を見ないこともあるが、その未知の味、未知の道具、未知の空気が醸し出す多種多様の「予感」がページに充満している。越田さんの料理写真は、匂い立ち脳内を駆ける。つまり、プラトン的でなくハイデッガー的な写真なのだ。
と、ひとしきり熱く語ったところで、スペースが足りなくなってしまった。
ともあれ、こういう種類の料理写真もあることを是非みなさんにも知ってほしかったのです。
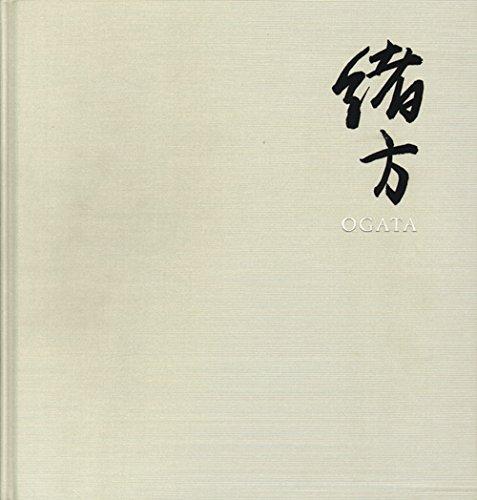
ケトル vol.40 Decenber 2017に寄稿