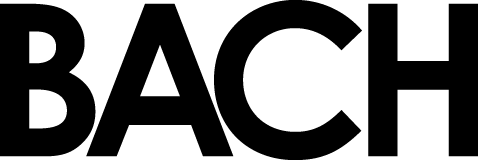幅允孝はいう。 何はともあれ、宮本常一の「土佐源氏」を読んでくれ、と。
とつぜんですが民俗学者 宮本常一の『忘れられた日本人』に収録されている「土佐源氏」を読んだことがありますか?
もしNOなら、今すぐ渋すぎる岩波文庫の表紙を本屋で探すか、百歩譲って電子本屋で
「ぽちっ」として欲しいところ。名も知らぬ高知・土佐梼原の乞食が語るオーラルヒストリーが、世に溢れる物語を凌駕することをあなたは知るだろう。
宮本常一は日本各地の農村、漁村、島を踏査し独自の民俗学を築いた男。フィールドワークのため16万キロ歩き(地球4周分)、無字社会に生きる無名の人の話を聞き、泊まらせてもらった民家は1000軒以上。師の一人である柳田國男と比べても、とにかく彼は実践派だ。山口県須防大島の百姓という出自を生涯誇り、社会の底辺を支える同胞として様々な人の話を聞いて日本中を巡った。そして、歩きながら考え記す民俗学者として日本の地域社会を理解しようとした人だった。
民俗学を「内省の学」とし、人の暮らしの祖型を探った柳田とは違い、宮本は人の暮らしに統一された文化があったのかと疑問を持ち、農村と漁村の差異や、西日本と東日本の違いを大切にした。宮本のもう一人の師であり、金銭的にも支えた渋沢敬三は、「学者ではなく発掘者になれ」と彼に語ったという。
たしかに宮本の『忘れられた日本人』には、世界の「捉えにくさ」や「どうしようもなさ」
が、そのまま真空パックされ、類型をつくろうとする解説もない。だからこそ、現在の読者も魅了する余白があるのだと思う。
冒頭で挙げた「土佐源氏」は、四万十川の最上流部の橋の下に住む盲目の乞食から聞いた話を宮本が書き記したもの。元馬喰(牛馬の仲買人)の彼が、昔むかし自身が経験した上流階級の人妻たちとの「色ざんげ」を語るのだが、これが愁いを感じるラブストーリーとして読者の心に響く。
特に、文庫版P148の「秋じゃったのう。〜」の部分からは出色の出来映えである。語り部は急に饒舌となり、身分違いの2人の逢瀬は読者の心をつかんで離さない寓話のよう。その物語としての完成度から様々な人が宮本による脚色を考慮し、それに関する書籍も出ているくらいだ。だが大切なのは、名も無き誰かのことを、この本によって後世の人間が覚えているということだ。
宮本常一は、泥にまみれた庶民の生活の中に、人が生き続けるたくましさを見出した。
昔から民衆は理不尽を押し付けられ、しかも、それが無残な忘却のうえに組み立てられているという世界の残酷さを承知のうえで、彼は人の明るさを見ようとした。
昨今、テレビををつければ政治家や芸能関係者「色ざんげ」が溢れており、
しかも「不倫=悪」という規範の押し付けもムズムズする。
なんというか、全ての物事に×印をつけやすい世の中だ。
宮本がいうように、いずれ忘れ去られ僕らの小さな生だからこそ、彼らのようになるべく○を歩んでいきたいものでる。
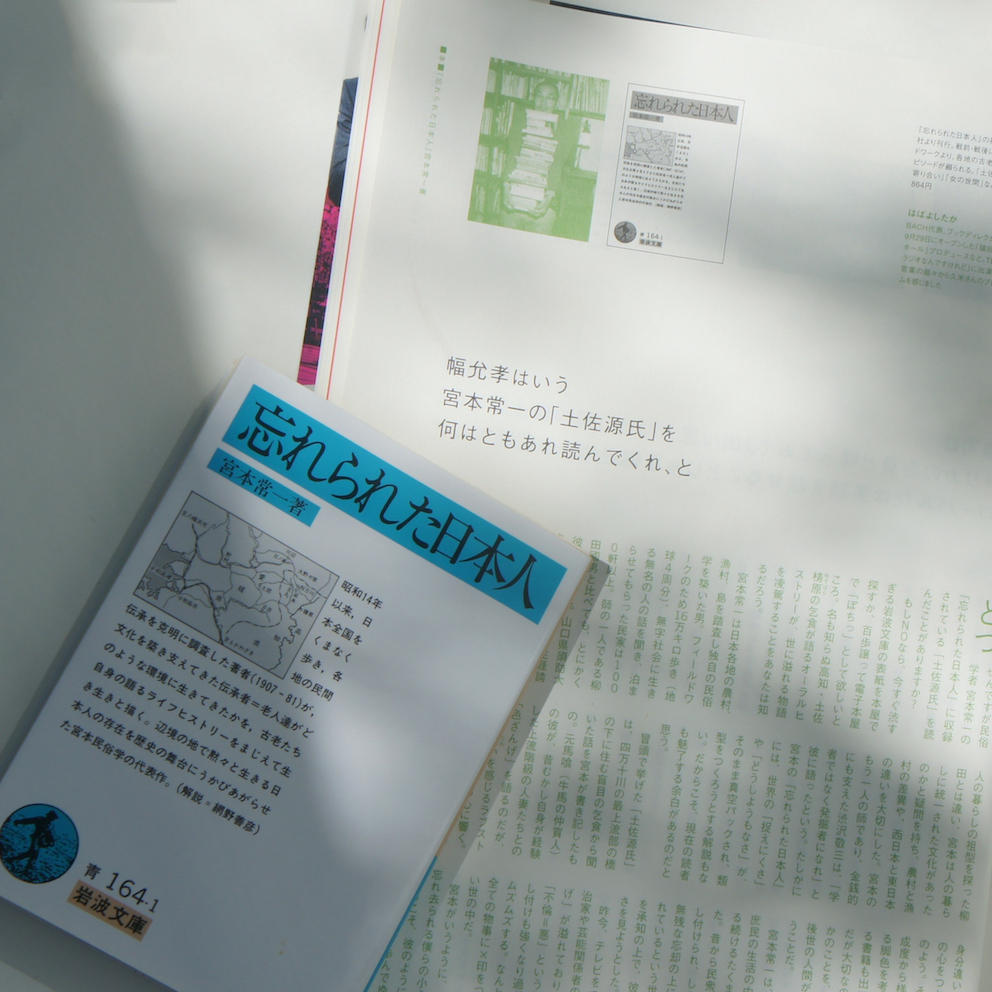
ケトル vol.39 October 2017に寄稿