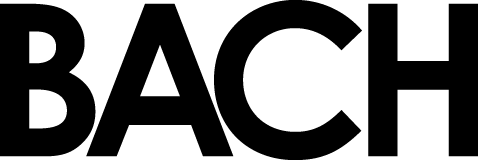幅允孝は、車谷長吉の小説が読み継がれて欲しいと切に願う
車谷長吉の小説『赤目四十八滝心中未遂』を初めて読んだ時、むせかえるような物語の匂いに気圧されてしまったものだ。
大学出のインテリだった主人公は、サラリーマン生活のぬるさに嫌気がさし、自ら孤独に堕ちてゆき世の中の暗がりを彷徨う。尼崎にたどり着いた彼は、狭く湿った暑い部屋で毎日臓物を串に刺す仕事を繰り返すが、ページの間からあんなにも肉の臭いが洩れてくる小説があるものかと僕は驚いた。それが車谷長吉という人が書く文章の凄みやおそろしさを直感した瞬間だった。
朝日新聞で連載した読者人生相談「悩みのるつぼ」では、つねに「人の本質は孤独」だと語り続け、教え子の女生徒に恋してしまった男には「破綻して、職業も名誉も家庭も失った時、はじめて人間とは何かということが見える」と説く車谷。実際、自らも慶應大学文学部を卒業し広告代理店に就職したものの、小説を書き続けるうちに仕事を辞し、関西で旅館の下足番や料理番などを転々とした私小説家というのが車谷の人生である。
もうひとつの代表作『鹽壷の匙』のあとがきで、彼はこんな文章を書いている。「小説を書くことは救済の措置であると同時に、ひとつの悪である。ことにも私が小説を鬻ぐことは、いわば女が春を鬻ぐに似たことであって、私はこの二十年余の間、ここに録した文章を書きながら、心にあるむごさを感じつづけて来た。併しにも拘らず書きつづけてきたのは、書くことが私には一つの救いであったからである。凡て生前の遺稿として書いた。書くことはまた一つの狂気である」。車谷長吉の物語=人生は、彼なりの誠実さと狂気が紙一重で展開している。
そんな車谷の魅力を書いた後に、今回はこんな最新刊を紹介したい。『夫・車谷長吉』。これは、2年前に急逝した車谷長吉を支えた詩人の妻、高橋順子が一人の小説家である夫を回想する1冊である。
「もし、こなな男でよければ、どうかこの世のみちづれにして下され」。こんな恐ろしい手紙をもらってよく恋に落ちたものだと思うかもしれないが、11通の絵手紙を通じた不思議な出会いは40歳を過ぎた二人の純潔な人同士を確かに結びつけた。彼らは結婚し、「くうちゃん」「順子さん」と呼び合い、作品世界の車谷とは違ったチャーミングな魅力を読者に振りまきながら夫は直木賞も受賞してしまう。順風満帆の日々である。
ところが、そのバランスは長くは続かない。車谷は脅迫神経症に悩み、酒量が増え、しょっちゅう手を洗い、ズボンの前を閉めなくなった。周りとの軋轢も絶えない。そんな夫を見守り支える切実さが、言葉の端々から伝わって来て頁をめくる手が止まらなくなる。小説を書き続ける夫の誠実さと狂気。それと真摯に対峙する高橋の眼差しを、愛と呼ばずして何と言うのか僕にはわからない。
世界一周の船旅、お遍路、不意の死別まで、妻の目から見た小説家の日々。こちらを読んでから車谷作品を味わうもよし、またその逆も然り。ともあれ、車谷長吉の作品が読み継がれてほしいと強く思える1冊だった。
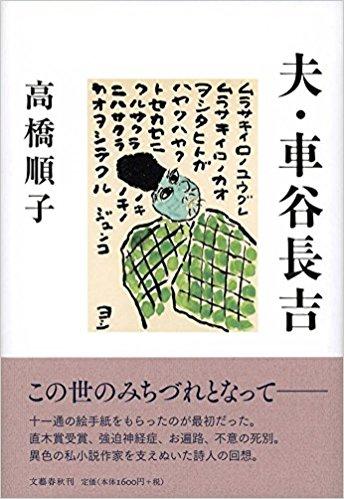
ケトル vol.37 June 2017に寄稿