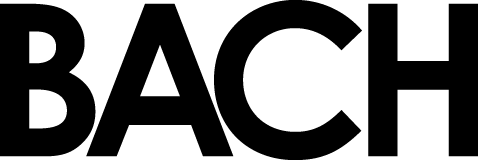幅允孝は『プリズン・ブック・クラブ』を読んで、 刑務所の見知らぬ読み手のことを想像する。
帯には、こんな言葉が記してある。「彼らが夢中になっているのは もはや麻薬ではなく書物なのだ」。この本は、カナダのコリンズ・ベイ刑務所から始まった読書会と、その運動の広がりを丹念に追ったノンフィクションである。
ぱっと聞くと、巷で見かける読書会とは随分ちがった様相を想像する方も多いだろう。それは、ある意味でYesだし、別の側面からみるとNoでもある。Yesの側面について書くなら、参加者の風貌は、さすがに迫力ある面子が揃っている。薬物がらみの事件で服役中のドレッドや、ヘルズエンジェルの元メンバーで薬物売買と恐喝により17年の懲役刑を受けている大男のグレアム。ほかにも、いかつくて厄介そうな刑務所の男たちが多々登場する。
ところが、そんなドレッドはカナダ人作家のマーガレット・アトウッドを愛読しているし、いつも周りとは違った視点で本の核心を射抜くグレアムは『サラエボのチェリスト』がフェイバリットなのだという。コンビニ強盗のピーターはスタインベックの『怒りの葡萄』とディケンズの『二都物語』がお気に入りで、連続銀行強盗をしたガストンは『ガーンジー島の読書会』が好きなのだとか。
もちろん、彼らは最初から読書家だったわけではない。だが、刑務所にいる彼らの怒りや喪失感や罪の意識や持て余した時間に、物語が染み込む余地があったのは確かなようだ。最初は、何となく参加していたメンバーもだんだん自発的な読書に変わり、やがて読んで湧きあがった意見を交換すること自体が楽しいと思えるようになっていった。「自分では気づきもしなかった点をほかのやつらが掘り起こしてくれる」と。
僕が本書に熱中できたポイントは幾つかある。例えば、語り部である「わたし」は、強盗未遂の被害に遭い犯罪者にトラウマを抱えている点。友人に誘われてこの刑務所読者会ボランティアに参加した彼女は、登場する収監者への警戒感が読者のそれと同じ位置からスタートする。だから、読者も主人公と犯罪者の間にある距離の変化を自然にトレースすることができる。
また、読者会のシーンも印象的だ。さながらそれは読者会の実況中継ともいえるような書き方で、取り上げる作品のあらすじや意味性よりも、その現場での白熱した議論を中心に話は展開する。収監者たちが、どの登場人物のどんな場面や言葉に心動いたのかを丁寧に描き、まるで読書会に参加しているように読める。未読の本は読んだのちに、この読書会シーンを読み直そうと思える程だ。
そして、もっとも納得できるのが、本の読み方の自由を書いている点。ひとつの物語をどんな風に読んでもいいし、他者の読みに対して寛容であることが、本を通じたコミュニケーションの基盤になることを本書は示す。白い紙の上の物語は人種や宗教や出自にも縛られることがない公平な場所。つまり、自身の心を開いてさえいれば、僕らも刑務所の中の彼らも何ら変わりのない唯のブックラバーなのである。

ケトル vol.33 October 2016に寄稿