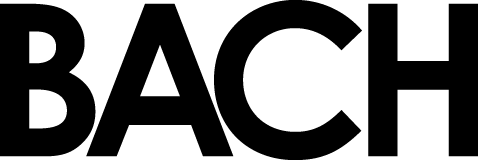幅允孝は『これを聴け』を読んで、批評ってこういうものだよねと思った。
アレックス・ロスの『これを聴け』を読んだ。原題は『LISTEN TO THIS』。彼は1968年にワシントンDCで生まれた音楽批評家で、1996年から「ニューヨーカー」誌の音楽評を担当している人物。前作の『20世紀を語る音楽』がピューリツァー賞の最終候補になったことでも知られている。
ロスは少年時代からクラシック音楽に親しみ、実際に自分でもハーヴァード大学で作曲を専攻していたという過去を持つ。「20歳になるまではクラシックだけを聴いて育った白人アメリカ人男性」と自らを呼び、その音楽遍歴のいびつさと「異様さ」を自覚しているところがまず面白い。同世代のクラスメートやガールフレンドたちが親しんでいたであろうロックやR&Bやヒップホップに興味を向けることもなく、一人水底に沈みながら音楽を聴いていた少年だったのかもしれない。
ところが、ロスは大学在学中に作曲の才能のなさを痛感。そして、自身が担当していた大学ラジオ局のクラシック番組直後に放送するパンク番組に出会い、ほかの音楽ジャンルへの興味を広げていくのだ。
数年後には、クラシック音楽のCDを売り払い、短髪にし、怒りを露わにしたTシャツを着てパンク・クラブでぶらぶらするようになったというから、ヒトの人生というのはわからない。ともあれ、そういったユニークな来歴を経た上で「クラシック音楽についてポピュラー音楽のように語り、ポピュラー音楽についてクラシック音楽のように語る」ことができる音楽批評家が誕生したのだ。
そういう意味では今作の『これを聴け』は、アレックス・ロスの真髄がわかる読み物といえるだろう。「ニューヨーカー」誌の連載に加え、書き下ろしも含めた20章からなる本書。モーツァルトを語っていたかと思えば、レディオヘッドのツアーに同行し、ヴェルディのオペラを通じて大衆芸術に触れたかと思えば、ジョン・ケージを通じて沈黙について考える。まさに縦横無尽。そして、その跳躍が決して力技でなく、とても理路整然とジャンル間の壁を越えてゆくところが、読後の心地よさと納得感なのだろう。
レディオヘッドの「クリープ」や「エアバッグ」で使われる「ピボット音」や「ペダル音」は、ロマン派の作曲家たちが繰り返してきた技法だと示唆するロス。ボブ・ディランが歌う「ブラインド・ウィリー・マクテル」とシューベルトの「冬の旅」の共通項を力説するロス。正直、僕は音楽の専門的なことはわからない。けれど、こんな風に細やかなひとつひとつの粒として音を聴けたのなら、どんなに楽しかろうと素直に思えたのだ。そして、読者が持たぬ知見から、ある世界を拡げてくれる批評こそが、本当に必要なものだと僕には思える。
4968円もするから決して安い本ではないけれど、長い時間をかけてゆっくり読み解けば、きっとその価値は伝わるはず。あと、日本人としてはマールボロ音楽祭で垣間見えるピアニスト内田光子の素顔と、日本でもファンの多いビョークの作曲法のページは読み応えがあると思いますよ。

ケトル vol.31 June 2016に寄稿