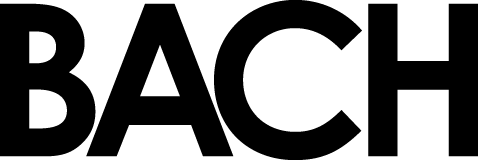跳ねた青森の夏
「とにかくアキレス腱だけは気をつけてください」。祭が開始する直前、みちのく銀行の菊池さんが念押ししたのはそれだけだった。彼はこう続ける。「あとは思うがままに楽しんで!」。これから書くのは、僕が初めて体験した青森ねぶた祭で受けた驚きと感銘の手記である。
誰でも参加できるねぶた祭
8月3日から青森県を訪れた僕は、その夜に「弘前ねぷたまつり」を見学した。青森ねぶたが戦の祝勝祭なのに対して、弘前のねぷたは戦へ向かう出陣の儀式を祭にしたものなのだそう。荘厳で、緊張感を孕(はら)み、山車の列も粛々と街を練り歩く。ちなみに弘前の祭りは「ねぶた」ではなく「ねぷた」。なんだかかわいらしい響きではないか。一言で「ねぶた」といっても最も有名な青森ねぶただけでなく、弘前ねぷた、近年人気の「五所川原立佞武多(たちねぶた)」など、多種多様な地域の祭があるらしい。恥ずかしいことに、そんなことすら知らずに僕はのこのこと青森までやってきていたのだ。
そもそも、ねぶたという祭の起源は諸説あるようだ。河合清子の『ねぶた祭 "ねぶたバカ"たちの祭典』(1)によると、坂上田村麻呂が蝦夷征伐の際に敵をおびき出すために大灯籠をつくったという伝承が紹介されている。また、柳田國男の書いた『年中行事覚書』(2)には「眠流し考」というページにこんな言説が記されているという。暑く農作業も忙しい夏に睡魔を遠ざけるため、1日で7回水浴びをして7回ご飯を食べるという「眠り流し」の風習。それが七夕行事とくっつき、「ねむた流れろ、豆の葉はとまれ」と唱えながら、灯籠や人形を川に流す行事になったとか。「ねむた」から「ねぶた」になったという説である。
そんなこんなのねぶた祭だが、最も大きな特徴として挙げられるのは、寺社が司るのではなく街の行事(民族風習)として自然発生的に広まった点だろう。つまり、寺の檀家でもなくとも、神社の氏子でなくても、誰でも参加できる祭ということだ。ハネト(跳人)と呼ばれる踊り手の衣装を身につけていれば、どんな人だって踊りの列に加わることができる。そして、前日の弘前ねぷたでは沿道からの見学のみだった僕が、翌8月4日の青森ねぶたでは急遽(きゅうきょ)参戦することになったのだ。知人の紹介でみちのく銀行の運行に交ぜてもらうことになったのである。
「ラッセラー」の掛け声とともに
みちのく銀行の衣装は、浅葉克己がデザインしたという勇猛な赤黒の浴衣。じつに勇ましいが、残念ながら僕の中では緊張感の方が上回っていた。都内の居住地区周辺の祭にすら参加したことのない男が、いきなりのねぶた祭デビューである。踊りも掛け声もわからぬまま、さあさあと促されるまま祭の行列に加わった。
時刻は午後7時5分前。今宵も祭が始まるぞという熱気が、四方八方から伝わって来る。青森の言葉で「じゃわめぐ」というらしいが、血の騒いだ者たちの声出しも始まり、いよいよスタートが近づいてきたことを実感する。青森ねぶた祭は8月2日から7日まで6日間行われ、今日は3日目。明日、明後日と行われる審査の前日だが、ウオーミングアップなどといったヤワな言葉は許されぬ。毎日が本番。毎日が真剣。みちのく銀行に所属する初代ハネトの野澤俊さんに「ラッセラーラッセラー」という掛け声と左右交互に足をケンケンする動きを教授してもらい、アキレス腱伸ばしを再度念入りにして祭の始まりである。
国道4号線からスタートしたわれわれハネトの前には、前ねぶたという小型のねぶたがあり、後ろからは祭の主役とも言える巨大な人形灯籠、大型ねぶたが続いて来る。その後ろには囃子方が続き、大きな太鼓や笛、手振り鉦の音が踊り手を活気づける。彼らの奏でるリズムに押し出されるように、僕の初ねぶたも前に進みだした。
正直に言うと気恥ずかしかったのは、最初の5分だけだった。周りの老若男女が腹の底から声を出し、楽しそうに跳び踊るのを見て、自分もそこに溶けていきたいと思った。ハネトとはよくいったもので、文字通り跳ねる動きを続けていると、どうしようもなく汗が出る。祭の前に飲んだビールも日本酒も、すぐに汗で流れてしまう。そして、菊池さんがアキレス腱の心配をするわけだ。これはかなり足腰にくる。だが、自身が踊るたびに衣装についている小さな鈴がシャンシャン鳴り響き、涼やかさと心地よさも与えてくれるのだ。この小さな鈴はラッキーチャームとしても知られているらしく、踊りの合間に沿道から「鈴ちょーだーい!」と子供が大声をあげている。ひとつとって沿道の少年に投げたら、未来の名外野手(?)は綺麗にジャンプして捕ってくれた。
6日間に込められた熱情
跳ね続け、足はすぐにパンパンに。拡声器で掛け声をかける男や女の声はかれかかっている。けれど祭は続く。なぜなら、それは気持ちよいからだ。見たことはないけれど、脳内でエンドルフィンが分泌されているに違いない。大きなポリバケツに入った水を柄杓で汲み、みなで回し飲む。こんなうまい水は味わったことがないぞ。
この熱気は、青森の街に暮らす人々の矜持になっているのだと思った。冬の気候も、人口減少も、地方経済の問題も厳しいけれど、この6日間の熱情があればきっと生きていける。それだけのエネルギーがこの祭には渦巻いている。そして、9時に祭が終わった直後の余韻と爽快感といったら、言葉には置き換えられない類のものだった。
青森は夏の始まりが遅く、終わるのが早い。帰り道、新青森駅まで乗せてくれたタクシー運転手は、「ねぶたが終わったら、もう夏も終わりだと寂しくなっちゃうんです」と話してくれた。「若い時みたいに毎日踊りはしないけど、結局祭の囃子を聴くと今でも体が動いてしまう」とドライバーはいう。「僕は今日からが、本番。今年も死ぬ気で跳ねてきますよ」という彼の顔は、心なしかもう紅潮していた。もう業務も終わらせて、跳ねにいっちゃってください!
幅 允孝
『SANKEI EXPRESS』2015.8.9 に寄稿
http://www.sankeibiz.jp/express/news/150809/exg1508091120002-n1.htm