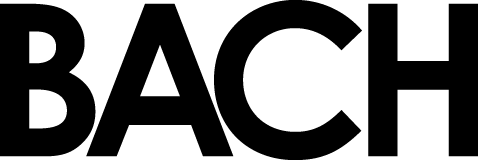読むことを通じて、京都と出会いなおす
本を読むのも好きだが、人から本の話を聞くのが好きだ。その人の中に深く刺さっている本について聞くと、その人の内側に少しだけ触れたような気持ちになる。もちろん完全に理解できるなんて思わないけれど、その人の紛うかたなき本質を垣間見ることになる。
誰かが本を語るとき、それは自分語りにもなっている。本自体が一人でしゃべり出すことはない。本を読んだ人が、自身の感じたことを、自分なりに話すことによってしか、本は誰かに伝わらない。
先ごろ僕は、京都に住むさまざまな方に、本について語ってもらう機会を得た。「三度目の京都」というウェブコンテンツをつくっている京都在住の写真家、中島光行さんが編集長を務める『本の中の、京都。』という書籍の監修に関わったからだ。そして、この「京都人の語る京都本」によって、僕は京都と出会い直すことができた。まずは、僕が書いた序文を部分的に引用させていただきた。
根っこに近い部分で
僕は京都の人間ではありません。友人たちはいるけれど、住んだこともなければ、血縁があるわけでもない。だから、一生観光客のままでいいと思っていました。「そうだ」と思いたったとき新幹線に乗り、寺社や庭を眺め、時候のおいしいものを頂き、大いに酒をのむ。そして、また東京に帰っていくのです。
そんな僕が、京都の写真家 中島光行さんに会って、少し欲が出てきました。最初の晩、このまちで生まれ育った彼は、自身が二十年以上も前にアルバイトをしていた小さな居酒屋に僕を連れていきました。当時から変わらぬ大将がつくる味はどれも絶品。なのですが、何よりも驚いたのは、その居酒屋が纏(まと)っている空気にです。近所の人がふらりと来ては、だらだらしゃべり、少し「あほぅ」な冗談をいい、「おもろい」話にみなで笑う。奇人変人、大いに結構。しかもみんなが痛風持ち。
京都の裏側を垣間みた。という単純な話ではありません。誰もが描く京都人のステレオタイプとは明らかに違う生の京都を実感したとき、僕は「なんだ、あんまり変わらないな」と自然に思えたのです。京都を京都たらしめていたのは、京都に住まない僕らでした。そして、京都に暮らす様々な人と、それぞれの根っこに近い部分で話をしてみたいと思ったのです。
この『本のなかの、京都。』では、京都に暮らし、ゆかりが深い20人に「御自身が京都を感じる本」を選び、それについて語って頂きました。本というのは不思議なことに読み手を映す鏡みたいなところもありますから、ひょっとしたら語らう彼らの根っこが表れるかもしれません。根っこは見えなくても、若筍の芽を土下に感じるくらいはできるかもしれない。
ともあれ、この京都人の紹介する京都本案内を通じて、あなたが京都と出会いなおしてもらえれば幸いです。みながつくった京都のイメージを脱ぎ捨てて、自分だけの京都を見つける愉しさを、ここに並ぶ本たちは媒介してくれるはずですから。(『本の中の、京都。』序文から)
自分の縦糸と、見つけた横糸
京都の老舗旅館「柊家」の女将、西村明美さんは、川端康成の『古都』について話をしてくれた。京都にある呉服問屋の娘、千重子と生き別れになった双子の姉妹・苗子の数奇な運命を描いたこの小説。そんな物語の中で、西村さんが心奪われたのは、花見の場面なのだという。千重子が平安神宮へと花見に出掛け、八重のしだれ桜が連なる美しい場面。
ところが、千重子は艶やかな桜の木々から少し外れたところにある一本桜の方が好きだと語り、重なった花の隙間からのぞく若葉の大文字山に見とれる。その「咲き誇る桜だけでなく、まわりの景色も一緒に」見る姿勢が、じつに京都らしいと西村さんは語るのだ。
庭も、街の人々も、市街を囲む山々も、空も、互いが引き立てあってひとつの風景をつくり、「その調和の中に『美』を見出そうとする」京都。祇園祭の一体感や、毎朝自宅の前を掃除する習慣、庭の借景などもすべて「まわりを生かし、生かされる」京の文化からきているのではないかと西村さんは話し、それを読んだ僕は、自然と何度も頷(うなず)いているのである。
京都の最北、花背にある料理旅館「美山荘」の当主、中東久人さんは、父の書いた『京 花背 摘草料理』という本から、先代の思いを読み解く。細見美術館の館長、細見良行さんは、千宗室『茶の心』を読み、日本文化の「背骨」を感じる。清水寺の執事補、大西英玄さんは、京都新聞の連載を書籍化した『日本人の忘れ物 京都、こころここに』に日本ならではの心の在り方をみつける。伝統的な本や、歴史小説、京都の中華料理の本もあれば、最近の京都の空気をつかみとるような雑誌の紹介もある。本の舞台が京都でなくとも、京都人を通して出会った本は、すべて京都にまつわる本になってくる。
「序文」でも記したが、京都に住まない人にとって、その街はなぜかいつも特別な場所だった。そして、旅行などで訪れたひと時だけ、京都を部分的にかじる。もちろん、そんな観光もいい。けれど、せっかく京を訪れ、実際の鴨川の土手に座るだけでも、あなたは京都の「縦糸」を手にしていることになる。そして、京都についての本を読むことは「横糸」の役割を果たすと僕は思うのだ。碁盤の目のようなこのまちには幾つもの横糸があり、それを頼りにすれば京都に住まない者にだって、一枚の織物をつくれる気がする。誰かの記憶や物語から、自身の京都を編み込んでいくということは、存外愉快な旅のやり方だと僕は思うのだ。
幅 允孝
『SANKEI EXPRESS』2014.12.11 に寄稿
http://www.sankeibiz.jp/express/news/141211/exg1412111545003-n1.htm