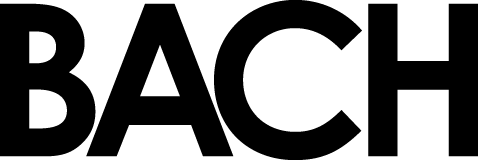幅允孝は『西加奈子と地元の本屋』という小冊子を大阪で見つけた
「大阪の本屋 発行委員会」がつくる小冊子『西加奈子と地元の本屋』が、とても熱くて素敵だった。実はすごく薄い冊子で、わずか32ページ、351円(税別)。けれど、そこに籠っている熱は、本に関わるあらゆる人を、ちょっとだけ奮い立たせる何かがあったのだ。
大阪・心斎橋にあるスタンダードブックスに立ち寄ったときに、偶然手に取ったこの1冊。どうやら大阪の書店員たちが中心となって作った小冊子らしい。冒頭は、その本屋で行われた西加奈子と津村記久子との対談から始まる。作風は違えど、まさに「大阪的」な作品を生み出す同じ年の2人。彼女らが語る「大阪を書く」話は、なんだか気持ちのよいペースで進んでゆく。
愛知で生まれたけれど、人生の半分以上を東京に住んでいる僕にとっては、確かに「大阪的」なことで、よくわからないことが幾つかある。大阪人がいう「おもろい」の後ろ側に含まれるもやもやした余韻や、なんで彼らはしゃべり止まないのだろう?といった単純な疑問などなど。そんな大阪にまつわる頭の?マークが少しだけ溶けたような気がする愉快な対談なのだが、僕の驚きは対話の後半部分に潜んでいた。
「東京的」なものへの突っ込みも程々に、2人の近作に話が及んだときのことだ。最近映画化もされた西の『円卓』の執筆について、彼女自身は「作家は、事実をそのまま書くのではなくて、その時に感じたり思った"粒"みたいなものを手を変え品を変え書く」と話したところから、対話は核心に迫る。「大阪」や「東京」といった地域性よりも、より対象に肉薄し「すごく近しい」ミクロの世界を描くことこそが、多くの読者にひろがる可能性があると語った西に対して津村が応えた「すべての場所がローカルである」という言葉にぐっと胸ぐらを掴まれのだ。
どこの場所であったとしても、必ず誰かの故郷だと認めることができたなら、差異よりは共有できることに興味も向いていくのだろう。実際、彼女たちの対談は、本の業界という今となっては小さくなってしまった舟に同乗する書き手や配り手や売り手をまとめるグルーヴ感を生み出しながら見事に着地した。出版業界のローカリティだって、こんな風に捉えれば、前向きな見方になるものなのだ。ちなみにこの対談は、西加奈子の語る最高のプロレス話などを交えながら進んでゆく必読の内容。にこにこしながらすぐ読み終えてしまった。
また、この冊子の読みどころは編集後記にもある。この本の制作に関わった書店員らが短い言葉を寄せているのだが、いままでは近所のライバル同士だった本屋が、こういうプロジェクトにより肉薄することで何だかノーサイドになっているではないか。より近くになると、些細なものなど気にならなくなるものらしい。
ミクロな方向に近づくことで、今までとは反転した流れを生んだ大阪の出版関係者たち。彼らの奏でるグルーヴが、東京だけではなく各地に広がり、いつか大きな物語を書き換える日がやってくるのかもしれない。

『西加奈子と地元の本屋』(大阪の本屋実行委員会/140B、380円+税)
ケトル vol.21 October 2014に寄稿