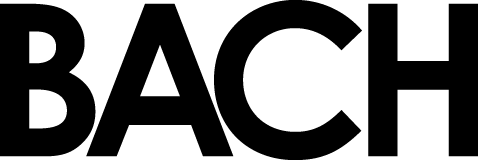幅允孝は、かつて子供だった自分を思い出せないでいた。この本を読むまでは。
加古里子のつくった『だるまちゃんとてんぐちゃん』という絵本がとても好きだった。ひげ面でいかめしい達磨が、なぜか子供の側にいるのが不思議で愉快だった。今でも子供の典型といえば、あの我が侭でわんぱくな「だるまちゃん」を思い浮かべてしまう。この『未来のだるまちゃんへ』は、そんな加古が絵本作家として生きてきた来歴を語りおろした彼の最新刊だ。
敗戦の時、加古里子は19歳だったというから今年でもう88歳をむかえる。小さな頃、彼は航空士官になりたかったのだという。だから、飛行機乗りに必要な数学や理科は勉強したけれど、国語も歴史も必要ないと全部切り捨ててしまったそうだ。だが、極度に進んだ近視のため軍人にはなれず、同級生たちが特攻で散ってゆくなか、生き残る。いや、彼の言い方を借りるなら、「死に残った」というわけだ。
そんな「死に残り」の加古が、その先の人生で絵本作家という仕事をするようになったことには、強い意志があった。彼なりの、生きる「よすが」を必死に探した果てに、なぜ彼は子供たちに向けた日々を選んだのか?
その道のりを、彼とともに振り返るのは実に愉しい読書となるだろう。特に幼少期のエピソードは微笑ましい。優しいけれど勘違いばかりの不肖の父。最初の師匠であり生涯の師だった同じ長屋に住む「あんちゃん」。なんてことのない毎日なのに、そこには物語が溢れている。
一方、芥川龍之介をライバル視するような文学青年だった加古が戦争のうねりに巻き込まれていく様は、時代の趨勢に対していかに個人が無力なのかを思い知らされる。東京大学の工学部化学科に入学したものの、空襲の延焼を防ぐために街中の木造住宅を引き倒す日々。そして、敗戦。
1945年の8月14日まで正しいとされていた価値が180度転換してしまった日本。「一億総懺悔」というお決まりの言葉ばかりが走り出し、まるで被害者のような顔をする人間ばかりが増えたと加古はいう。政治が無能なのは今も昔も変わらないが、加古の疑念はすべての大人たちに向けられた。何もかも嘘っぱちに思えた世界。そんななかで加古が師として選んだのは、「最も鋭い観察者」と彼が呼ぶ子供たちだった。
戦後、川崎のセルツメント(市民ボランティアのようなもの)を手伝い、そこに集まってくる悪ガキたち相手に一緒に遊び唄った加古里子。その現場に居続けることが彼の絵本制作へと繋がってゆく。加古の言葉を借りていうなら、セルツメントの「子供へのメッセージを絵入りで示しているうちに」たまたま絵本になってしまったというわけだ。
冒頭にも書いたように彼は今年で88歳だが、1945年で一度死んだ人間だと本人もいっているので、まだ69歳ともいえる。そう、彼は大先輩であるものの同時代人でもあるのだ。先人の箴言ではなく現代人の生の声として、この本に耳を傾けなければならない。加古の眼を通して見えてくる世界の在り方、子供への想いの寄せ方は、すべての元・子供たちに響くはずだ。
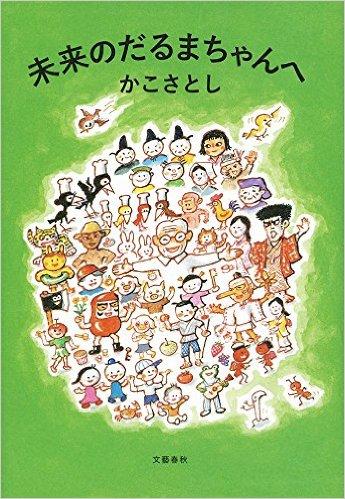
「未来のだるまちゃんへ」(かこさとし著/文藝春秋、1,450円+税)
ケトル vol.20 August 2014に寄稿