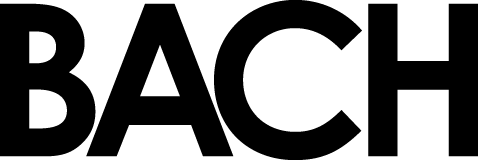人が生きていくのに写真は必要か?
それが、途方もなく長い道のりになることは、誰もが覚悟していたはずだった。
当然のことながら、僕らは毎日を何とか生活してゆかねばならないし、一方で、風化とはまた別の、記憶との自発的な距離のとり方をさぐる術も、少しずつ会得しながら生きている。
3年という時間の前に対峙する
東日本大震災からもうすぐ3年になる。このほど発表された『津波、写真、それから』(1)という大判の本は、津波で流されてしまった写真を持ち主の手元に返そうとした活動の記録を、写真と文章でまとめたものだ。そして、3年という時間を積み重ねた僕らだからこそ、ここに並ぶ写真たちと、やっと対峙(たいじ)できるのではないだろうか。
そのプロジェクトを牽引(けんいん)した何人かを代表する形で、高橋宗正という写真家の名前が本書にはクレジットされている。高橋のことは2010年に出版された『スカイフィッシュ』(2)という写真集で知っていた。「アンテナを全開に」しながら「思考をパタッと閉じて」写真を撮ると自ら語る彼は、日常のなんでもない瞬間を独特な切りとりかたをする。
なんというか、写真行為という作為の向こう側にあるものをつかもうと、もがいているようなすがすがしさを写真集から感じたのだ。「なぜ写真を撮るのか?」ということを常に自分にぶつけながら、「生きる」ということと「撮る」ということを同化させたいと願う高橋。そんな彼が、震災を目の当たりにして、このようなプロジェクトに、持てるだけの時間と労力をささげ続けることができたのは、彼自身の写真性と深く呼応しているようにも思えた。人が生きていくのに写真の力は必要なのだろうか? 高橋は、このプロジェクトを通じて問い続ける。
プロジェクトの始発点は、福島県との県境に近い宮城県亘理郡山元町にある小学校の体育館だった。その中にはずらりとプラスチックのケースが並び、ケースの中にはアルバムや流された写真がいれられていた。災害支援の活動中に自衛隊や消防などが集めたという膨大な量の写真は、約75万枚という途方もない数。それらの写真を、洗浄し、データ化する「思い出サルベージ」プロジェクトのボランティアとして、東京に暮らす高橋は自身と震災の結節点をみつけてゆく。
津波に流され、泥のついてしまった写真を、慎重に水につけながら、ハケで優しくこする。そうやって洗浄した写真は、日影で乾くまで干し、次にデータ化の行程にまわされる。
あまり電気が使える状態ではなかったので、ここではスキャンではなく自然光で写真自体を撮るという方法が選ばれた。三脚とカメラを方々から集め、何人ものボランティアが写真の写真を撮る。ひたすら流された写真を撮影し続ける。そして、毎週末20~80人の人が集まったこの「思い出サルベージ」は、驚くべきことに3カ月という短期間ですべての写真の洗浄とデータ化をやり遂げてしまったのだ。高橋も本書でこうつづっている。「人間やればできる」。
誰かが生きていた痕跡
次の段階では、きれいになった写真を持ち主に返さなければならない。写真が見つかった場所ごとにファイリングされた写真は、写真の返却室に整然と並べられ、丁寧にインデックスもつくられた。全てのページをめくらずとも、そのインデックスを眺めれば、自分のアルバムかどうかの判別がつくからだ。一方でデータベース化もされ、返却室に設置されたパソコンで閲覧できるようにもなった。さらには顔認識システムを活用することで、写真を探しに来た人と似た顔の写るアルバムを膨大なデータの中から見つけることができるようにもなる(本当に技術というのは使いようですね)。このようにして、3年間で30万枚の写真が持ち主に返っていったという。
さて、問題はここからだ。洗浄をしてみたものの、どうしても傷みが激しく、誰の写真か判別のつかないものが、作業が進むにつれて少しずつ、着実に、増えてきた。その写真をめぐって何度も話し合いがもたれた。処分してよいものか? 処分しないとするなら、どうするべきか?
日々の作業で多くの見知らぬ人の写真を眺め、洗い、撮影してきた彼ら。そこに写る被写体は、生きている可能性も、亡くなってしまった可能性もある。そんな風に会ったことのない誰かを案じながら、一方で、確かに誰かが生きていたという痕跡をたどった彼らの出した結論は、その写真たちを展示することだった。写真展「LOST&FOUND PROJECT」の始まりだ。
震災と自分の自然な距離感
この写真展とともに世界中を巡ることになった高橋の旅の結末は、ぜひ本書を読んで確かめてほしい。静かな死をいつも傍らに抱えながら、彼は写真の意味を考え続ける。一方で彼の道程は、現地に居らず、被災を免れた者にだって、自分と震災の結節点をみつけることができることも強く示唆する。
それは、高橋のように直接現地と関わるかたちもあれば、遠くにいながら想い続けるというかたちもあるはずだ。自分が日々考え、興味を持っていることと、震災のある側面を近づけてみる。そうすると、出自のわからぬ後ろめたさや記憶の後退とはまったく別の、震災と自分の自然な距離感と、それについて考え続けるための持久力が備わる気がする。僕たちは、まだまだこれからも、考え続けなければならないのだ。
幅 允孝
(1)「津波、写真、それから」(高橋宗正著/赤々舎、2730円)
3.11の津波で流されてしまった家族写真を、持ち主に返そうとした活動を1冊にまとめる。写真家の高橋宗正による写真と文章は、写真という存在が、人の生活の実際的な何に作用してきたのかをあぶり出す。
(2)「スカイフィッシュ」(高橋宗正著/赤々舎、2940円)≫
高橋宗正が写真という表現方法によって何を伝えたいのかを知るには、この1冊が相応しいだろう。物語性を拒み、何げなく撮ったばらばらの写真をずっと眺めていると、あら不思議。通底する何かが見えてくる。
『SANKEI EXPRESS』2014.4.6 に寄稿
http://www.sankeibiz.jp/express/news/140304/exg1403041546003-n1.htm